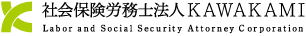介護休業取得の判断基準に障害児・医療的ケア児等も明記
厚生労働省は今年1月、労働者の家族が介護休業制度の対象となる状態であるかを確認するための判断基準を見直し、公表しました。
従来の基準は高齢者を想起
育児介護休業法の介護休業等の対象者は「要介護状態」にある家族を介護する労働者です。この要介護状態とは「2週間以上に渡り、常時介護を必要とする状態」をいいます。介護休業は対象家族がいる場合、本来、その家族が高齢者であっても、子どもであっても取得ができます。
しかし、この「常時介護を必要とする」かどうかの判断基準については、特別養護老人ホームへの入所措置基準を参考にするなど、主に高齢者介護を念頭に作成されており、子どもに関する判断基準の記載がないため、障害児や医療的ケア児等を持つ労働者が介護休業の取得を希望した場合に対象となるのか解釈が難しいという声があがっていました。そこで、「常時介護を必要とする状態」に関する判断基準の見直しがおこなわれました。
障害児等も念頭においた基準へ
見直された点を具体的に紹介しましょう。
まず、「障害児や医療的ケア児等を介護・支援する場合」にも、介護休業等が利用できることが明示されました。また、「常時介護を必要とする状態」の判断要素となる項目の一部に、次のような文言が追加されました。
・「危険回避ができないことがある」
発達障害等を含む精神障害、知的障害などにより危険の認識に欠けることがある障害児等が自発的に危険を回避することができず、見守り等を要する状態をいいます。
・「認知・行動上の課題がある」
例えば、急な予定の変更や環境の変化が極端に苦手な障害児等が、周囲のサポートがなければ日常生活に支障をきたす状況をいいます。
・「医薬品または医療機器の使用・管理」
従来の「薬の内服」という表現から、注射薬、外用薬や人工呼吸器、経管栄養にも対応できるような表現とされました。