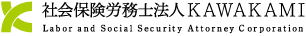時間単位年休の導入
時間単位年休の導入には就業規則で制度内容を定め、労使協定を締結する必要があります。対象者の範囲、時間単位で取得できる日数(年5日分まで)、1日分の時間数、賃金の計算方法などを決めておきましょう。
年次有給休暇(年休)は、通常「1日単位」や「半日単位」で取得するのが基本ですが、時間単位年休はこれを「1時間ごと」に取得できる制度です。たとえば、通院や子どもの送り迎え、銀行や役所での手続きなど、短時間だけ仕事を離れたい場合に、必要な分だけ有給休暇を使うことができるため、労働者からのニーズが高い制度です。
管理が煩雑になることから導入に消極的な企業もありますが、社員のワークライフバランス向上、定着率アップやイメージの向上など、企業側にもプラスとなる制度です。
時間単位年休は、今後さらに使いやすくなるよう法改正も検討されています。ここでは、時間単位年休の導入方法や注意点について解説します。
時間単位年休を導入するには
時間単位年休の導入は、会社の自由であり、法律上の義務ではありません。ただし導入をする場合は、就業規則に規定し、労使協定を締結する必要があります。労使協定については、労働基準監督署への届出は不要です。
労使協定に記載する事項
時間単位年休を導入する際、労使協定には以下の事項を記載する必要があります。
◆対象者の範囲
時間単位年休の対象となる労働者の範囲を定めます。一部の労働者を対象外とする場合は、「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られます。取得目的によって対象範囲を限定することはできません。
◆時間単位年休の日数
時間単位で取得できる年休は年5日分(40時間)までのされています。なお、今後この上限の緩和が検討されています(2025年度中に結論が出る見込み)
◆時間単位年休1日分の時間数
1日分の年休が何時間分に相当するかを所定労働時間数をもとに定めます。
<例>
(1日分の年次有給休暇に相当する時間単位年休)
第〇条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1日の年次有給休暇に相当する時間数を8時間とする。
所定労働時間に1時間未満の端数がある場合は切り上げて設定します(例:7時間30分の場合は8時間)。日によって所定労働時間が異なる場合は、1年間の1日平均所定労働時間数を基準とします。
◆1時間以外の単位で与える場合
「2時間」「3時間」など、1時間以外の単位で取得を認める場合は、その時間数を定めます。ただし、「15分」「30分」など細かい単位は認められず、基本は1時間単位となります。
就業規則に定めるべきこと
就業規則には、労使協定と同様に「時間単位年休の対象者の範囲」や「時間単位年休の日数」「時間単位年休1日の時間数」などを記載します。また、時間単位年休に対して支払う賃金額の計算方法についても明記しましょう。
賃金の計算方法は以下のいずれかから選択します。ただし、1日単位の年休と同じ方法にする必要があります。
① 平均賃金
② 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
③ 標準報酬日額(この場合は労使協定が必要)
時間単位年休1時間分の賃金額の計算式は次のようになります。
<<上記①~③のいずれか ÷ その日の所定労働時間数>>
変更後の就業規則は、労働基準監督署への届出が必要です。
時季指定義務の5日カウントされる?
時間単位年休で取得した分は、会社に義務付けられている「年5日の時季指定義務」の取得日数には含まれません。ですから最低でも年5日分は、1日単位または半日単位で取得してもらう必要があります。